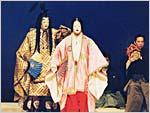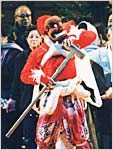|
|
| 第2回 地域伝統芸能まつり テーマ「恋(こひ)」 |
 このまつりは、宝くじの売上金から助成を受けて実施しました。 このまつりは、宝くじの売上金から助成を受けて実施しました。今年も多くの方にご応募いただいた「地域伝統芸能まつり」。4万人以上の方からご応募いただきました。応募いただいた皆様、誠にありがとうございました。厳正な抽選を職員総出で実施しました。(来年応募される場合は、必要事項をもれなく記入してくださいね) さて、当日。午後3時の開演時刻を迎え、静かに明かりが落ち、今年のテーマ「恋(こひ)」にちなんで、「ひょっとこ」と「おかめ」の恋の物語。続いて三味線にカッと眩しいスポットライト。今年はブレイク中の「木下伸市」の「津軽三味線」。超絶技巧で魂を呼び覚ますように激しくバチを打ち続けるさまは、まさに圧巻。さらに「地域伝統芸能まつり」のテーマ曲「曼陀羅21序章」を和楽器ロックバンド「六三四」が演奏し、福井県織田町の「明神ばやし」の子供たちが太鼓で見事に応ずると、お祭り好きは、いてもたってもいられない。出演者総出で、オープニングは盛り上がりました。 |
| 【司会】 |
 司会は昨年に続き2回目の葛西聖司(NHKアナウンサー)。そして、女優の竹下景子。それぞれ特色のある各演目を、テーマ「恋(こひ)」に結びつけて、演目を解説される方々と落ち着いた口調でわかりやすく紹介。そのポイントを押さえた紹介に、実際にはなかなか行くことができない日本各地に伝わる民俗芸能について、実際にご当地に行った気分になってご覧いただけたのでは!また、日頃は敷居が高く難しいと思われがちな古典芸能についても、鑑賞方法などのポイントを紹介・解説してくれることで、はじめて鑑賞される方も、親しみやすさを覚えたのではないでしょうか。 司会は昨年に続き2回目の葛西聖司(NHKアナウンサー)。そして、女優の竹下景子。それぞれ特色のある各演目を、テーマ「恋(こひ)」に結びつけて、演目を解説される方々と落ち着いた口調でわかりやすく紹介。そのポイントを押さえた紹介に、実際にはなかなか行くことができない日本各地に伝わる民俗芸能について、実際にご当地に行った気分になってご覧いただけたのでは!また、日頃は敷居が高く難しいと思われがちな古典芸能についても、鑑賞方法などのポイントを紹介・解説してくれることで、はじめて鑑賞される方も、親しみやすさを覚えたのではないでしょうか。 |
| 30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30日、31日ともに予定終演時間を超過して、終了しましたことを、お詫び申し上げます。 |
| 地域伝統芸能アンケートに寄せられたご感想 |
| ● | 全ての演目が素晴らしく、この機会を得られたことは、大変幸せです。あらためて日本の伝統芸能の素晴らしさ、奥深さを感じました。 |
| ● | 伝統芸能はその土地、地方に行かないとなかなか見られないので、東京で見られてとても感動した。次回も是非企画してほしい。 |
| ● | 北海道から沖縄まで受け継がれた芸能、地方色が豊かで楽しく拝見しました。 |
| ● | 小学生の後継者も出演してとても良かった。ますます伝統芸能が栄えるよう、そして、日本の文化に触れる機会を作ってください。 |
| ● | 地域振興のためにも、とても良い企画だったと思います。とても楽しく見せていただきありがとうございました。 |
| ● | 関心はあっても、そのチャンスの少ない日常です。楽しくかつ有意義な時間を過ごさせて頂きました。来年を楽しみにしています。 |
| ● | 地域のまつりが背景美術の効果もあり、自分自身も祭りに参加しているくらい迫力があり、地元の人たちの気持ちがこちらにまで伝わってきました。いつか、それぞれの県に行って本当に参加したいです。 |
| ● | 本当に本当に楽しかったです。多くの関係者に感謝申し上げます。ありがとうございました。病身でなかなか旅に行けませんので、すっかり旅をしたような気分です。又、企画して下さい。来年もぜひNHKホールで旅をしたいと思います。 |
| ● | 大変楽しく拝見しました。宝くじはこういう分野にも使われていることも初めて知りました。今後も伝統芸能と地域文化に触れる機会をつくっていただきたいと思いました。 |