沖縄の古典芸能であり、2010年にユネスコの無形文化遺産に登録された組踊。約70作品ある中から組踊の創始者・玉城朝薫が創作したといわれる朝薫五番のひとつ「孝行の巻」を映画化し、映文連アワード2022を受賞した『シネマ組踊 孝行の巻』が話題となっている。プロデュースしたのは東京に生まれ、国立劇場おきなわの開場スタッフになったのを契機に沖縄に移住した大野順美さんだ。2010年には組踊を中心とした沖縄伝統芸能の舞台制作を行うステージサポート沖縄を設立(2013年に一般社団法人化)。琉球芸能プロデューサーという肩書きで仕事をする大野さんに、組踊との出会いから映画のプロデュースまで、組踊に寄せる思いを寄稿していただいた。

(クリックで拡大表示)
大野順美(一般社団法人ステージサポート沖縄代表理事、琉球芸能プロデューサー)
「歌と踊りの島」と言われる沖縄。エイサーや沖縄民謡、カチャーシーなどは世間に徐々に浸透してきたが、古典芸能の存在はまだまだ知られていない。
かつて、沖縄は「琉球」という独立国家だった。琉球王国は他国からの様々な影響を受けながらも独自の文化を生み出していた。その最たるものが、今に伝わる「琉球古典芸能」だろう。琉球王府から続く伝統芸能には、琉球古典音楽・琉球舞踊・組踊などがある。それらの中で私は、縁あって伝統歌舞劇「組踊(くみおどり)」を中心にした琉球芸能のプロデュース等を行なっている。
●組踊との出会い
大学で日本の民俗芸能ゼミという珍しいゼミに所属していた時、演劇学概論の授業で1本のビデオを観た。伊江島にだけ伝わる組踊『忠臣蔵』だった。江戸から約2000km離れた小さな離島に忠臣蔵が存在することにカルチャーショックを受け、組踊の他の演目にも興味をもつようになった。
その流れで卒業論文でも組踊をテーマに取り上げた。論文を執筆している最中に文化庁が沖縄に組踊専用の劇場を開設することを発表した。卒業後は、新国立劇場、文化庁で勤務しながら組踊を鑑賞するために沖縄へ足繫く通っていた。私が文化庁の建造物課に配属されていた頃、隣の伝統文化課には国立組踊劇場(仮称)設立準備室が開設されていた。
その後、縁あって国立劇場おきなわの企画制作課に勤務することになり、開場記念公演において初めて仕事として組踊に携わることになった。東京では周りに組踊はおろか琉球芸能を知る人は皆無だったが、沖縄へ移り住み、劇場で働くと「琉球芸能を説明しなくても解ってくれる人がこんなにもいる!」という喜びが大きかった。しかし同時に、出演者はその道のエキスパートばかりで、それまで休日に沖縄へ通うだけだった東京人の私にはとても太刀打ちできず、働けば働くほど己の知識不足を痛感した。

●疲弊する実演家をサポート
こうして劇場で働きながら思うことがあった。琉球古典芸能の実演家は、ほとんどの人が昼間別の仕事で働いており、本業である舞台の仕事だけで生活しているステージプロはほとんどいなかった。舞踊家の中には自身で道場を経営し、レッスンプロとして自活している人もいるがそれほど多くなく、ことに若手は皆無だった。
また、公演の主催が団体であれ個人であれ、制作業務は“事務局”という名前で演者本人たちが担っていた。第三者に委託できるほどの予算もなく、古典芸能は関係者と非関係者の理解度に差があり過ぎるため(つまり、知っている人はマニアック過ぎて、知らない人は知識ゼロ)、外部の人に任せられない。そもそも当時の沖縄には“舞台制作”という言葉はないに等しく、制作業が業務として認識されていなかった。
つまり、実演家の道を歩むためには、「収入が得られる昼間の仕事」「舞台表現者としての活動」「その活動を成立させるための制作業務」、この3つをこなさなければならない。加えて、古典芸能は自分だけが努力すれば良いわけではなく、師匠から習って初めて成立する。舞台表現者として師匠の元に通いながら並行して自分の舞台にも立つわけだから、いくら時間があっても足りない。国立劇場おきなわの定期上演が始まって少しずつ状況が変わり始めたところもあるが、公演を開催しても儲かるわけでもない。肉体的にも経済的にも疲弊していく。
そんな実演家たちを少しでも助けられないだろうかというモヤモヤを抱えていたため、沖縄県立郷土劇場を運営する(公財)沖縄県文化振興会に移ってからは、夜や休日に組踊に関わる仕事を何でも引き受けるようになっていた。その後、フリーの舞台制作者として独立した。当時、琉球芸能関係団体のほとんどが任意団体であり、行政からの受託事業や助成金申請に不都合が生じていた。「それなら私が舞台制作業務を行う法人を立ち上げることで、実演家たちが技芸に専念できる環境を作れるのでは」と考え、2013年に法人化した。
事務所の名称は一般社団法人ステージサポート沖縄。「こんな公演がしたい!」という自分の夢のために立ち上げたわけではなく、そういう夢を抱く実演家をサポートすることを第一の目的として、プロデュース業を行なっている。


ちなみに、私はおこがましくも琉球芸能プロデューサーと勝手に名乗っている。それは私がなりたいからというより、花屋という職業を知っていてはじめて子どもたちが「将来花屋になりたい」と夢を抱くように、私が専門職業として名乗ることで後進が続くかもしれないと期待しているからである。
●分母を増やす
かつて恩師である三隅治雄氏が「琉球芸能にはスターが必要だ」と言われた。組踊の立方・地謡の誰でもいいから東京の芸能事務所に所属し、ひとりでもTVや映画で顔と名前が売れてくれれば、組踊の知名度が上がるだろう、と。しかし、沖縄に住み琉球芸能の現場で仕事をするうちに、私はこの恩師の言葉が正しいのかどうか、なんとなく疑問に感じるようになった。
確かに組踊関係者は観客増加を誰もが願っているが、果たしてこうした方法で増やすことを望んでいるのだろうか? とはいえ、組踊の知名度を上げなければ”未来が無い”ことも解っている。人口減少が加速する日本において、次世代の実演家や観客の育成は待ったなしだ。
世界で活躍する日本人ピアニストが大勢いるのは、ピアノ人口が多い、つまり“分母”が多いからだとすれば、組踊も分母を増やすしかない。バレエを見たことがない人でも「チュチュを着て踊っている姿」はイメージできる。歌舞伎を見たことがない人でも「隈取りと派手な衣裳で見得を切る姿」はイメージできる。では、組踊は? イメージできる人はほとんどいないのではないか。国指定の重要無形文化財なのに!
今、この日本、この沖縄は、組踊の立方・地謡のスターを育てるどころの状況ではなく、まずは組踊自体の認知度を向上させることが必要なのだ。私は恩師の言葉に、自分なりの答えを出した。「スターが育つ環境を作るため、まずは分母を増やす」。
そのために、公演プロデュースの回数をとにかく重ねた。沖縄県内で琉球芸能団体の公演制作に協力し、組踊創始者・玉城朝薫生誕300年の記念行事を県へ提唱し、また県外出身であることも幸いしてか県外公演も多く手掛けた。能楽・神楽・京劇など他ジャンルの伝統芸能との比較上演やコラボレーションも積極的に実施した。異種の役者同士が互いの伝統芸能を理解する機会にもなり、また、他の伝統芸能の観客に組踊を知ってもらうことにも繋がった。

(クリックで拡大表示)

(クリックで拡大表示)

(クリックで拡大表示)

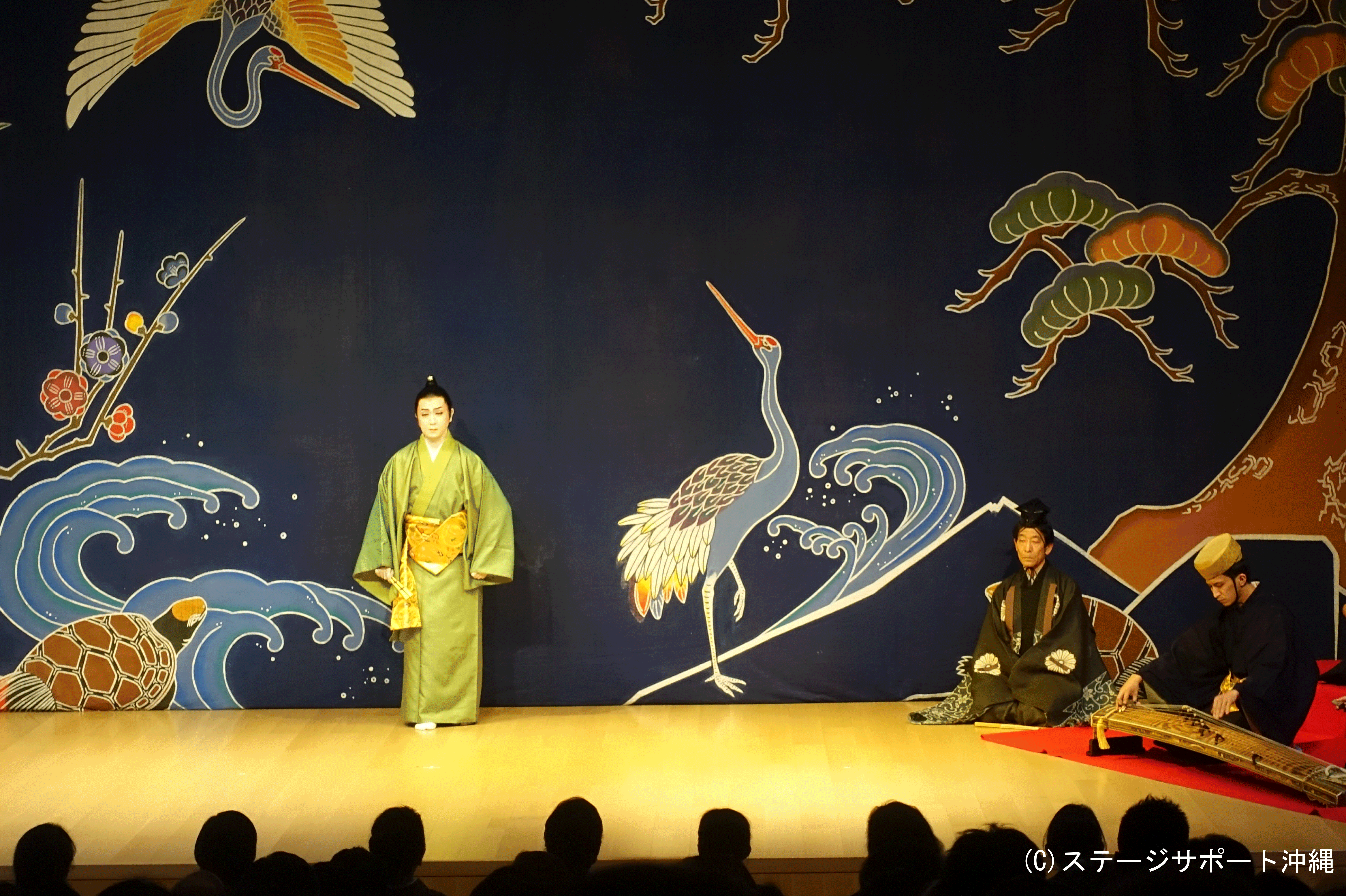

コツコツと地道に、できる限り上質の公演を続けてきたつもりだが、このまま続けても1.2億人の国民には一生かかっても届けることができないと、ある日ハタと気が付いた。そこで考えたのが映像の力を借りることだった。
●シネマ組踊
2014年に組踊『二童敵討』、翌15年に組踊『執心鐘入』の2作品が浦添市によって映画化され「シネマ組踊」と名付けられた。私も舞台マネジメントと解説脚本執筆に携わった。映像なら一定のクオリティが約束されたものを多くの人に見てもらうことができる。上映期間中ならそれぞれの観客の好きなタイミングで観に行く事もできる。ただ、このシネマ組踊はあくまで浦添市への観客誘致を目的としたものだった。
モヤモヤした気持ちのまま数年が過ぎた頃、過去2作で同じチームだったスタッフの横澤匡広氏(のちの共同プロデューサー)から「組踊の映画をまた作ろう」と声をかけられた。相当悩んだが、私がやらなくても誰かがやるのなら、それでクオリティが低くなるくらいなら、自分でやった方がいい。そう腹を括った。また、コロナ禍がいつまで続くか先が見えない中、舞台を再開できる時節をただ待つよりも、映像なら“飛沫の飛ばない組踊”として届けられるという理由もあった。
こうしてシネマ組踊の3作目『孝行の巻』の製作が始まった。現在70演目ほどある中で『孝行の巻』に決めたのは、組踊の創始者玉城朝薫が創ったとされる五番の中の、過去2作を除いた3作のうち、「舞台で上演する場合は大掛かりな仕掛けがあって、県外では上演機会が少ないことから、映画なら迫力を損なうことなく全国へ届けることができる」という理由からだ。
監督は『アンを探して』で国際映画祭「第5回アジアン・フェスティバル・オブ・ファースト・フィルム」最優秀作品賞と最優秀監督賞の2冠に輝いた、宮平貴子氏。出演者キャスティングは大野、撮影スタッフ選定は横澤氏、とお互いの専門を生かすことで、最高の布陣を整えることが出来た。特に出演者は、人間国宝など高度な技能よりも、長時間の慣れない撮影に耐えうるだけの体力を持つ役者であることが必須条件であるため、中堅・若手を中心とした。普段なら1年先でもブッキングが難しいほど人気の演者を勢揃いさせる事ができたのは、実はコロナ禍で舞台の仕事が減っていた時期だったことが幸いした。
はじめに話し合ったのは撮影方針だった。まず、地謡(演奏者)の演奏位置。通常公演では幕内・正面奥出囃子・上手出囃子の3種類がある。今回の映像では地謡も見せたいという希望があったものの、長時間の撮影で正座し続けるのは厳しいということもあり、王朝時代と同じ紅型幕の後ろ(紗幕なので地謡は立方の演技が透けて見える)で演奏することにした。そして、組踊の見どころ聴きどころなどを事前にスタッフへ説明し、台本や過去の映像を見ながら撮影監督とともに入念にカット割りを決めていった。
撮影は、2021年の緊急事態宣言直後。丸3日間国立劇場おきなわの大劇場を借り切って、レールやクレーンなど大掛かりな撮影機材を持ち込み実施した。初日に本番同様に通し上演を撮影し、残り2日間で個別のズームやクレーンなど初日に撮れなかったシーンを撮り直した。この方法により演者・演奏者の集中が途切れず気持ちの乗った映像を撮影することに成功した。

左上:本編|右上:地謡の演奏|左下:案内役による解説|右下:標準語字幕
出演者は、同じシーンを何度も撮り直したり、連日同じ化粧・扮装にしなければならないなど、普段の公演とはまったく違う演技・演奏の仕方に戸惑いや苦労もあったようだ。一方、「1つの演目に連日集中して取り組んだことで大きな学びを得た」という声もあった。コロナ禍で舞台の機会を失った10代・20代を起用し、先輩と同じ現場で技能を学んでほしいという気持でキャスティングした効果があったようで嬉しかった。
琉球版ミュージカルともいわれる組踊には「聴きに行く」という言葉があるほどなので、音の調整も入念に行われた。拍子木の音1つにしても、3日位かけて丁寧に調整した。共同プロデューサーの横澤氏は数々の邦画を手掛けてきた音響プランナーでもあるため、立方の唱えや地謡の音楽は生の舞台に引けを取らない上質なものとなった。
本作が前2作と異なるのは、民間企業が一般劇場公開用映画として製作した点だ。映画は公演記録映像とは本質が全く異なる。再演や後世に残すことが目的ではなく、映像を通じて組踊を理解し魅力を知ってもらうことを大前提に、エンターテイメント映像として楽しめることが第一の目的である。そのための工夫として、組踊の上演形式そのものは全く変えず、カメラによる多角的な撮影だけではなく、本編に入る前にナビゲーターが歴史やみどころなどを案内する“解説編”を加えた。
また、日本語字幕にも注力した。『孝行の巻』は朝薫五番の中でも対句が多い演目であり、対句表現の美しさも観客に知ってほしい気持があったが、表示字数が多くなれば文章に気を取られ映像を見逃してしまうため、監督と話し合った結果、字幕表示は1文字でも字数を減らし、かつ中学生程度でも理解できる言葉選びに努めた。完全に意訳の部分もあるが、物語の世界観を壊さない程度に一瞬で頭に入ってくる文章を心がけたつもりである。見巧者や研究者にとっては納得いかない和訳もあるかと思われるが、“伝統芸能”というだけで避けてしまう層を取り込むことを優先した結果である。
伝統芸能を見慣れない人にも理解しやすい工夫をする一方、絶対に譲れなかった点は「本編ノーカット」である。YouTubeやTikTokなど短編動画に慣れている若年層には長編鑑賞が厳しいかもしれないが、組踊は“間”を楽しむ芸能であるため、ダイジェスト映像にするのは本質を違えてしまう。生の舞台と同じ時間軸で鑑賞してもらうことで「次は公演に行ってみようかな」と思ってもらえることを期待していた。
完成した映画『シネマ組踊 孝行の巻』は、翌22年「沖縄国際映画祭」にワールドプレミア特別招待され、 監督や出演者は3年ぶりに復活したレッドカーペットへの出演を果たした。その後、沖縄県内では桜坂劇場・沖縄市音市場・宮古パニパニシネマなどで上映され、翌23年、東京渋谷ユーロスペースを皮切りに大阪・京都・神戸・横浜・名古屋・仙台・宇都宮・広島・佐賀・福岡など全国主要都市での上映も行われた。おかげで「組踊を全く知らなかったけど、いつか実際の舞台を観に沖縄へ行きたい」という声を多数いただくことができた。また、映像文化製作者連盟主催の映文連アワード2022においてパーソナル・コミュニケーション部門優秀企画賞も受賞した。

もちろん、華々しいことだけではなく苦労もあった。製作費はなんとか工面できたものの、配給宣伝費まで手が回らないのだ。映画業界では“宣伝費不足はインディペンデント映画ならばよくあること”と言われるものの、「せっかくの作品をお蔵入りさせてはいけない」という思いから、配給会社がクラウドファンディングを立ち上げてくれた結果、宣伝費を何とか集めることができた。この活動は、資金集めと同時に映画の前宣伝にもなるという良い効果も生み出してくれた。
今後は、修学旅行で沖縄を訪れる中高校生に滞在ホテル等で夕食後のコンテンツとして本作を楽しんでもらえないかと画策している。伝統芸能は若い世代から触れておくのが肝要だと自分の経験から強く思うため、将来の観客になるであろう10代に組踊を発信したいと思っている。
全国民に組踊を好きになってほしい、とは言わない。「組踊という2文字を覚え、組踊が踊り(dance)ではなく演劇(play)であることを全国民に分かってもらう」ことが私の野望である。
●「生きる喜び」としての文化の力
さて、先日初めて韓国へ赴いた。2024年6月23日(慰霊の日)に合わせて、能と組踊と韓国の伝統芸能の合同公演を東京・高円寺で実施するため、出演者の調整に行ったのだ。初めて生で見る韓国の伝統芸能農楽(ノンアク・プンムル)の迫力に圧倒されたが、それ以上に農楽にかかわる人たちのパワーに感動した。生命の輝きというのはこういう事かもしれないと感じた。
かつて沖縄も芸能にこれだけの地力を持っていたはずなのに、今はシャイで合理的なZ世代の背中に身を潜めてしまっているのだろうか。人間が生きるためには衣食住が必須だが、なぜ生きたいと思うか、生きる喜びを実感できるのは実は芸能文化の力にゆだねられている所が大きいように思う。生命をつなぐ医療や福祉ももちろん大切だが、文化は己のアイデンティティそのものだ。
生命が輝くようなキラキラした一瞬に出会えれば、自分の生きる意味が発見できることがある。私は、私に「好奇心」という生きる力を与えてくれた組踊に今日も心を支えられながら、組踊がいつかバズる日を夢見て、1人でも多くの人に届ける仕事を続けていきたい。
大野順美 プロフィール
東京生まれ。新国立劇場、文化庁を経て、2003年国立劇場おきなわの開場スタッフとして沖縄に転居。(財)沖縄県文化振興会で沖縄の文学・古謡の事業を担当。2010年に組踊を中心とした沖縄伝統芸能の舞台制作を行うステージサポート沖縄を設立(2013年に一般社団法人化)。沖縄県内外や海外での公演を手掛ける。映文連アワード2022を受賞した映画『シネマ組踊 孝行の巻』プロデューサー。
